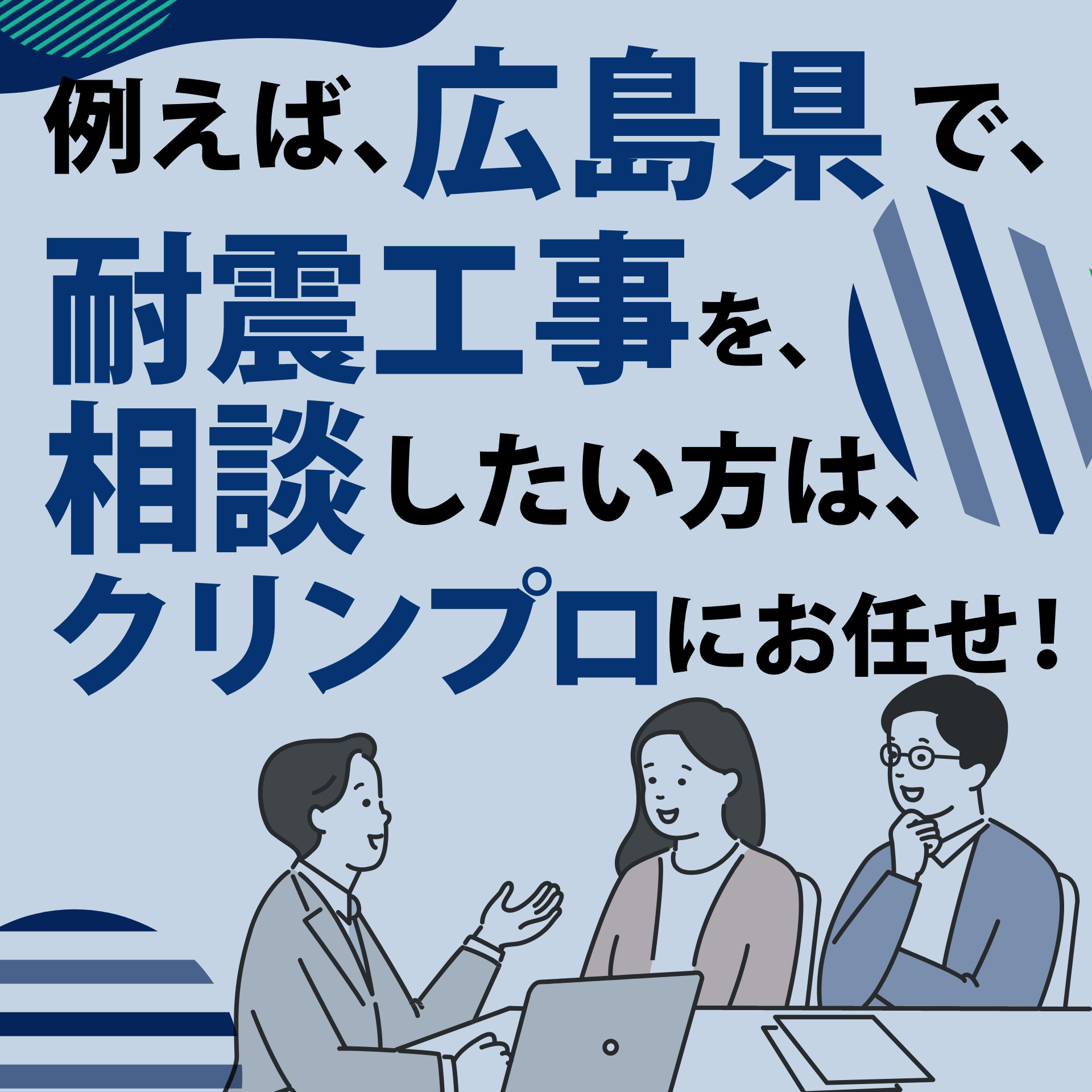2025.12.01
老朽化した住まい。解体?リノベーション?どっちが正解?
2025.09.01
地震はいつも突然に起こる。起こってからでは遅いのです。だからこそ、耐震補強。
広島県の安芸太田町は、県内でも人口減少率が高い地域の一つとされています。
この先も南海トラフ地震や首都直下地震など、大規模地震の発生が高い確率で予測されています。
皆さんの「備え」、特に住宅の耐震化は万全でしょうか。
命や財産を守るためにも、この機会に耐震補強を考えてみませんか。
阪神・淡路大震災では10万棟以上、東日本大震災では12万棟以上の家屋が倒壊・崩壊しました。
住宅は一瞬にして失われることもあれば、危険な状態のまま時間をかけて倒れていくこともあります。
住宅の倒壊は、避難経路や救助活動の妨げにもなります。住宅密集地では隣家や通行人への二次被害の恐れがあり、火災の原因になるケースも少なくありません。
まずは、今の住まいの状態を知ること、つまり「耐震診断」を受けることが大切です。
特にチェックしたいのが、家が1981年6月以降に建てられたかどうか。
この年、宮城県沖地震の被害を受けて建築基準法が改正され、より大きな地震に耐えられる「新耐震基準」が導入されました。
熊本地震では、1981年5月以前の木造住宅は被害なしが約5%に対し、新基準では約31%。倒壊・崩壊は旧基準で約28%、新基準では約7%と、大きな差がありました。
まずは耐震診断を行い、必要があれば耐震改修に踏み切りましょう。

(一財)日本建築防災協会が提供する「誰でもできるわが家の耐震診断」では、3択の質問に答えるだけで耐震リスクを把握できます。(国土交通省住宅局監修)
質問例:
•建築時期(1981年6月以降/以前/不明)
•災害被害の有無(床上浸水・火災・地震など)
•増築の有無と手続き
•傷み具合や補修の履歴
耐震性の理解や改修計画の参考になります。ぜひ一度お試しください。
誰でもできるわが家の耐震診断

耐震診断から改修までの流れは次の通りです。
1.予備調査・現地調査(図面や現況確認)
2.耐震診断(専門家による耐震性能評価)
3.耐震改修計画(必要な工事内容の検討)
4.耐震改修設計
5.工事費の見積もり
6.耐震改修工事
改修方法には、屋根材を軽量化する、壁や柱を補強する、基礎を強化するなどがあります。
建て替えよりも短期間で済み、住みながら工事できる場合も多く、費用面でも負担が軽くなります。
業者選びに不安があれば、まずはお住まいの自治体窓口に相談を。
専門業者や支援制度の情報が得られます。