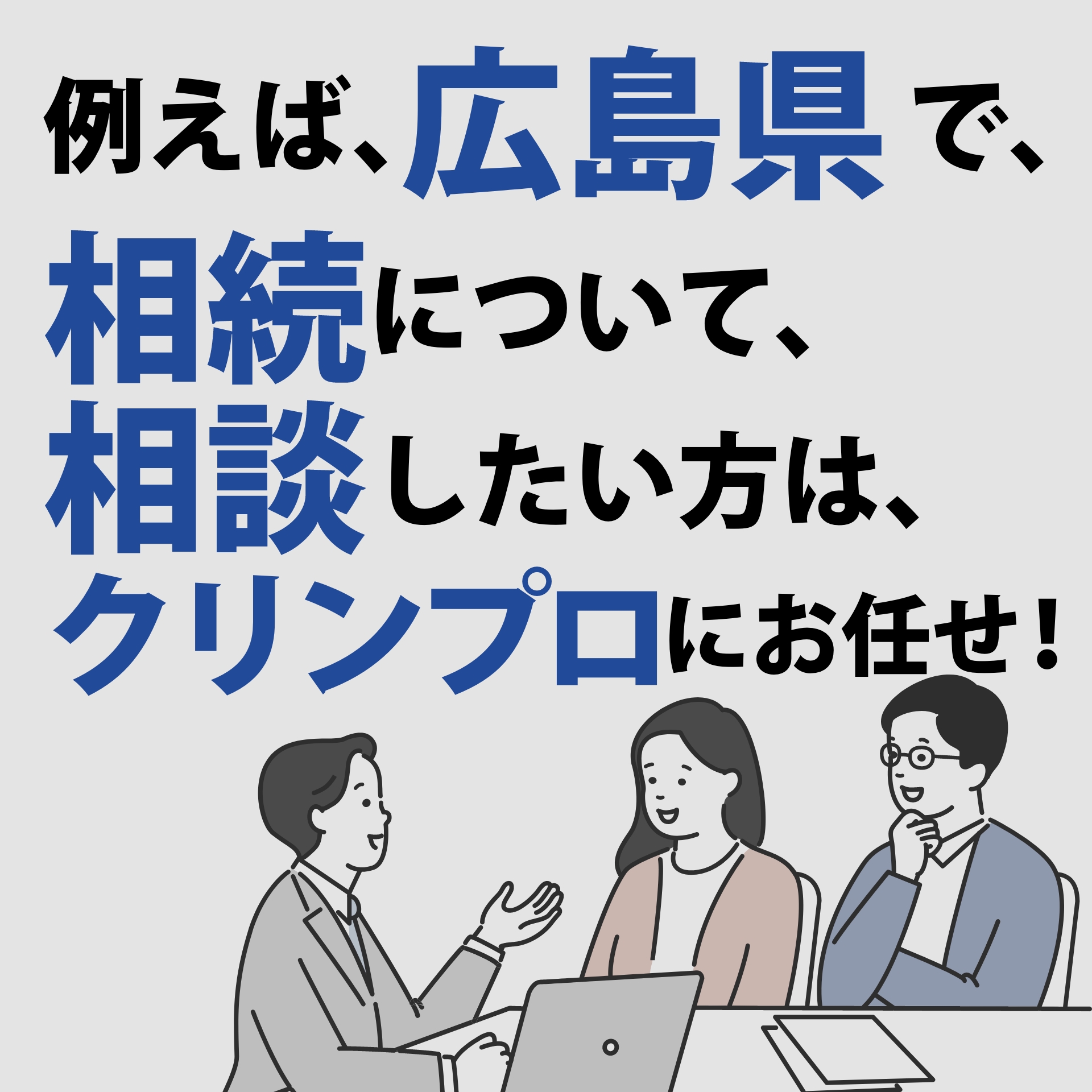2025.12.01
老朽化した住まい。解体?リノベーション?どっちが正解?
2024.09.01
わが家の相続の顛末。 すべて、実話です。
我が家の相続のてん末についてご紹介するブログの最終回です。
結論から言うと、完全な失敗であったわけですが、今回は、その理由についてお話しようと思います。皆さんの参考になれば幸いです。
相続、つまり法律を侮ってはいけないということを、心に留めておいてください。そして、その時がきたら、我が家の失敗を参考に立ち向かってください。
第一回:母の遺した借地権。どうすればいい?
第二回:兄弟間の分配。思わぬことに。
第三回:まさか!税金取られるの?
前回までの簡単なおさらいですが、母が亡くなり、借地権という財産を姉弟3人で相続することになりました。
借地権は簡単に売れるわけでもなく、仮に買主が見つかっても、どうせ二束三文に買いたたかれるのだろうと考えていました。
しかし、ラッキーなことに我が家の隣の土地を購入した開発業者が、一緒に開発したいと、申し出てくれたのです。金額も相場どおり。とんとん拍子に話が進み、無事に契約できました。
その後、姉弟で多少の意地の張り合いはありましたが、弁護士さんの説得もあり、代金を3等分した金額がそれぞれに振り込まれました。
ただ、相続税など税金のことが頭の片隅には、引っ掛かっていました……

相続税はどうなるのか?そもそも、借地権の分配ですから、世間的にもそれほど大きな金額ではなかったのに……
その不安は日に日に、募りました。
そして、この際、税務署に聞くのがいいだろうと、所轄の税務署に相談という形で赴きました。担当の税務署職員に、ことのなりゆき、そして現在の状況などを話しました。
すると、いわゆる空き家特例が該当する可能性が高いとレクチャーを受けました。なんと、3,000万円まで特別控除されるというのです。それは、もちろん3等分した金額の範囲内です。これで控除を受けられれば、めでたしめでたし!と、勇んで姉弟にも伝えました。
帰宅して、素人ながら、税務署から配布された資料を確認してみると、「区分所有建物登記されていない」「昭和56年以前に建築されている」など、特例の対象となる幾つもの条件を満たしているではないですか。母が亡くなり、借地権やその上に建つ建物は空き家扱いになる!と、思い込んで安心していました。

そして、迎えた確定申告。相続用の用紙を取りに税務署へ行き、自宅に帰ってもろもろ記入を始めました。
すると、どうも引っ掛かる部分が出てきたのです。それは、「被相続人居住用家屋等確認書」というものを添付しなければならないということでした。
初めて見る文字。そして、これは資産の所在地を所轄する市区町村長から交付されるものでした。暗雲がたちこめたような気分になりました。
急いで該当の区役所に行き、詳しい話を聞きました。専門用語の羅列になるので、簡単に翻訳すると、買主には、土地と建物を一緒に売らなければならないということでした。
実際に借地権の土地の上に母が住んでいた建物はありましたが、売買の話が出た後に、先に建物を解体していたのです。買主は土地だけを必要としていたので、解体費用も買主が負担するということで、それは願ってもない話だと喜んでいたのでした。そしてその後、実際の契約に至った。
つまり、解体の日より後の売買契約で、私たちは土地だけを売ったというカタチになっていたのです。

当然、区役所にも、税務署にも掛け合いました。「こんな内容は知らなかった。」「初めて聞いた。」「知っていたら対策を考えていた」など。
しかし、門前払いです。愕然としました。えええええ!という感じです。
結局、どうにもならず、税金だけが当然のように取られていきました。きちんと調べ切っていない自分自身が悪いのですが、「あの時、税務署でひと言言ってくれれば」と悔やみました……
詳細は端折りましたが、これが我が家の相続の結末です。
もしも、今後、相続に直面することがあれば、専門家にアドバイスを受けることをお勧めします。今更ですが、素人では太刀打ちできません。もし、相続に関しての正しい知識を持っていれば、余分な税金を支払わなくてもよかったという慙愧に絶えない出来事でした。
どうか、皆さんは私のような失敗をせずに、相続を乗り切ってください。